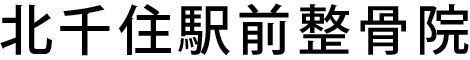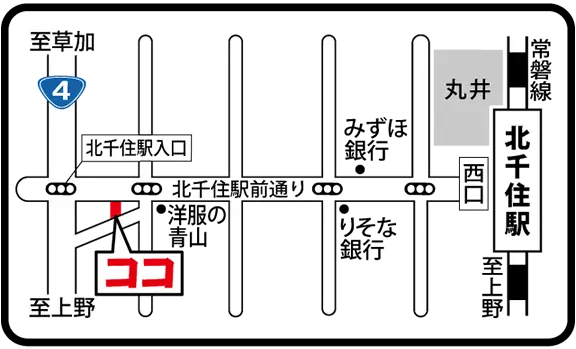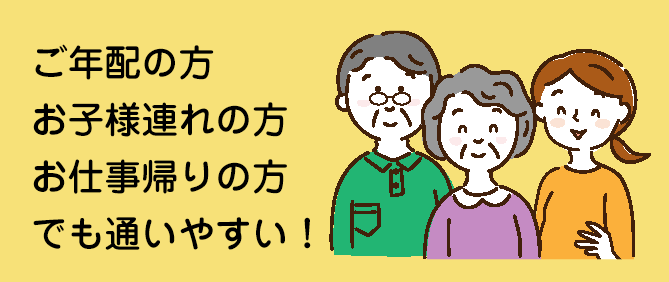最近、こんな症状に心当たりはありませんか?
• 肩がなんとなく重い
• 腕が後ろに回らない
• 夜中に肩がズキズキする
• 洋服を着るときに肩が痛い
• 高いところのものが取れない
もし「えっ、それ、あるある…」と感じたら、この記事を読み進めてください。
あなたの肩、もしかすると「五十肩」の入り口に立っているかもしれません。
⸻
「五十肩」とは?
五十肩(ごじゅうかた)とは、正式には**肩関節周囲炎(けんかんせつしゅういえん)**と呼ばれる病気です。
その名の通り、肩関節の周囲の筋肉や腱、関節包に炎症が起きることで痛みや可動域制限が出る疾患です。
「四十肩」とも言われることもありますが、基本的に同じものです。発症年齢の違いだけ。
40代でもなる人がいますし、60代でなる人もいます。
⸻
こんな症状、思い当たりませんか?【セルフチェックリスト】
以下に挙げる症状のうち、あなたはいくつ当てはまりますか?
✅ 肩を動かすと痛みがある
✅ 腕が上がらなくなった
✅ 背中に手を回せない(下着をつけづらい)
✅ 夜中、肩の痛みで目が覚める
✅ 電車のつり革につかまるのがつらい
✅ 髪を結ぶのがしんどい
✅ 肩がこっているのとは違う“ズキズキした痛み”がある
✅ 洋服の袖に腕を通すとき痛みを感じる
✅ 肩だけでなく腕や肘、手先までしびれるような感覚がある
✅ 湿布やマッサージでも効果がない
5つ以上当てはまった方は要注意です。
すでに五十肩が始まっているか、発症間近の可能性大。
⸻
放置していいの?
結論から言うと、放置は絶対にNGです。
「自然に治るんじゃないの?」という声もよく聞きます。
確かに五十肩は、時間とともに症状が緩和する「自然経過をたどる」疾患ではあります。
でも、それは1年〜2年かけての話。
その間、痛みによる生活の質(QOL)の低下は避けられませんし、放っておくことで肩の可動域が元に戻らなくなる(関節拘縮)リスクもあります。
⸻
五十肩の3つのステージを知ろう
五十肩には進行具合に応じて3つの段階があります。
① 急性期(炎症期):痛くて眠れない!
この時期はとにかく痛みが強いです。
何もしていなくても痛む「安静時痛」や、夜中の「夜間痛」が特徴。
腕もほとんど上がらなくなります。
② 慢性期(拘縮期):動かせない…
痛みは少し治まってくるものの、今度は肩が動かないという別の問題が出てきます。
関節が硬くなってしまい、可動域が狭くなります。
③ 回復期:少しずつ動くように
リハビリや治療を続けていくことで、徐々に動くようになってきます。
ただし、元の可動域まで完全に戻すには時間と努力が必要です。
⸻
原因は?なぜ突然なるの?
五十肩は、はっきりとした原因が特定できないことが多いですが、以下のような要因が関与していると考えられています。
• 加齢による関節や筋肉の変性
• 肩を酷使する生活(仕事やスポーツ)
• 血流の低下
• 姿勢の悪化(スマホ首・猫背)
• ストレスや自律神経の乱れ
つまり、日々の生活習慣や身体の使い方がじわじわと肩を壊しているということです。
⸻
病院に行くべきタイミングは?
「これって五十肩かな?」と思ったら、まずは整形外科を受診しましょう。
なぜなら、似たような症状を出す疾患が他にもあるからです。
【鑑別が必要な疾患】
• 腱板損傷(筋の断裂)
• 石灰沈着性腱板炎
• 頸椎由来の神経痛(肩ではなく首の問題)
• リウマチ性疾患
正確な診断には、X線やMRI、超音波などの検査が必要になることもあります。
⸻
五十肩の治療法は?
💊 薬物療法
• 鎮痛剤(ロキソニンなど)
• 湿布
• ステロイド注射(痛みが強い場合)
🧊 温熱・冷却療法
• 急性期は冷やす、慢性期以降は温める
(痛みの種類に応じて使い分けが必要)
💪 リハビリ・運動療法
• 固まった関節を少しずつ動かす運動がカギ
• 無理のない範囲で毎日継続することが重要
🧘♀️ 日常生活の工夫
• 肩を冷やさない服装をする
• 高いところの物を取らないようにする
• 重いカバンを片側だけで持たない
⸻
自宅でできる簡単ストレッチ(医師推奨)
※痛みが強い場合は無理をしないでください。
🌀 タオルストレッチ
1. タオルの両端を持ち、背中の後ろで上下に動かす
2. 痛い側の腕を下にして、もう一方の腕で優しく引っ張る
→ 肩甲骨周りの可動域を広げます
⭕ 壁を使った腕上げ
1. 壁に向かって立ち、指先で「歩く」ように壁を登っていく
2. 痛みのない範囲で高さを調整
→ 無理せず少しずつ可動域を広げる練習に最適
⸻
最後に:五十肩は「放置せず」「焦らず」治すもの
五十肩は、ある日突然やってきます。
でも、日頃の生活習慣・ストレッチ・意識によって予防もできますし、早期に気づけば重症化を防ぐこともできます。
あなたが「当てはまるかも…」と感じたら、まずはチェックリストを見直し、体の声に耳を傾けてください。
そして、何よりも大切なのは、
「年だから仕方ない」とあきらめないこと。
まだまだ動ける体を取り戻すために、今日から小さな一歩を始めてみましょう。