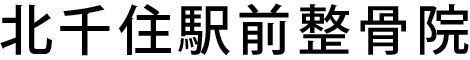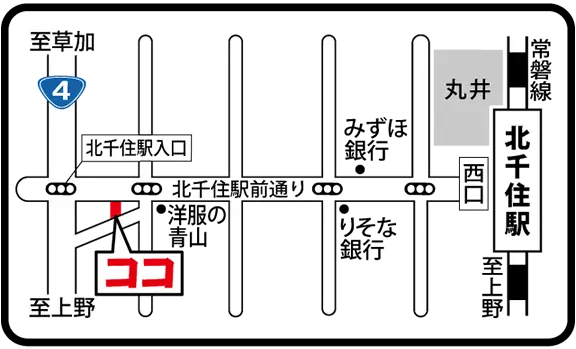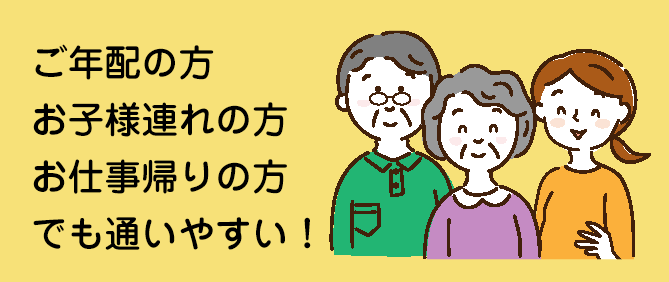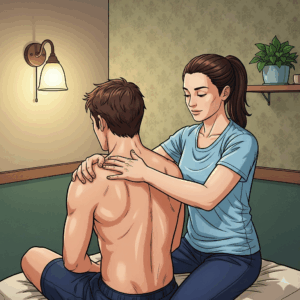
はじめに:肩の痛み、放っていませんか?
日常生活や仕事、スポーツで肩をよく使う人にとって、「肩を上げたときに痛む」「夜寝るときに肩がズキズキする」といった症状はとてもつらいものです。
それはもしかすると、「インピンジメント症候群」かもしれません。
この記事では、インピンジメント症候群の基本的な知識から、自宅でできるケア方法として注目されている肩甲骨はがしまでを徹底的に解説します。肩の痛みを軽減し、快適な日常を取り戻すためのヒントが満載です。
⸻
インピンジメント症候群とは?
インピンジメント症候群とは、肩関節で骨と筋肉、腱などの軟部組織が衝突し、炎症や痛みを引き起こす障害です。特に、腕を上げる動作や繰り返し肩を使う動作で痛みが強くなるのが特徴です。
主な症状
• 腕を上げたときの痛み(特に90度以上で痛みが増す)
• 夜間痛(寝返りを打った時の痛み)
• 肩の動きが悪い・引っかかる感じ
• 肩を動かすと「ゴリゴリ」「ミシミシ」と音がする
発症しやすい人
• デスクワークで長時間座っている人
• 猫背・巻き肩の姿勢が習慣化している人
• 野球・テニス・水泳など、肩を酷使するスポーツをしている人
• 高齢者(腱板が弱くなってくるため)
⸻
なぜ痛みが起こる?インピンジメントの原因
肩の関節は非常に自由度が高い構造をしていますが、そのぶん筋肉や腱、骨が密接しているため、姿勢の悪化や筋力のアンバランスによって摩擦や圧迫が生じやすくなります。
主な原因には以下のようなものがあります。
• 肩甲骨や肩関節の動きの悪化
• 肩周囲の筋肉(特にインナーマッスル)の弱化
• 肩の過使用(オーバーユース)
• 猫背や巻き肩などの姿勢不良
• 加齢による腱板の変性
これらの要因が重なることで、肩の骨(肩峰)と腱板の間が狭まり、腱板が擦れて炎症を起こすのがインピンジメント症候群です。
⸻
インピンジメント症候群の基本的なケア方法
1. 安静にする
まずは痛みを悪化させないことが第一です。
痛みが強い時期は無理に動かさず、重い物を持たない、肩を高く上げないなど、刺激を避けるようにしましょう。
2. アイシング(急性期)と温熱療法(慢性期)
• 急性期(痛みが強い時) → 氷で冷やす(1回15~20分程度)
• 慢性期(痛みが引いてきた時期) → 温めて血流促進(入浴・温湿布など)
冷やすか温めるかは、痛みの状態によって使い分けるのがポイントです。
3. ストレッチとリハビリ
肩まわりのストレッチやインナーマッスル(腱板)を鍛えるリハビリも有効です。
ただし、無理をせず、痛みの出ない範囲で行うことが大切です。
⸻
肩甲骨はがしが効果的な理由
最近注目されているケア方法に「肩甲骨はがし」があります。これは、固まった肩甲骨まわりの筋肉や筋膜をほぐして、肩の動きを改善するストレッチ・セルフマッサージです。
なぜ肩甲骨が重要なのか?
肩甲骨は肩の動きに連動して動く「土台」のような役割を持っています。
この肩甲骨が固まって動かなくなると、肩関節に過剰な負担がかかり、インピンジメントのリスクが高まります。
⸻
自宅でできる!肩甲骨はがしのやり方
ここでは、自宅で簡単にできる肩甲骨はがしのセルフケア方法を3つ紹介します。
⸻
① 肩甲骨まわりのほぐしストレッチ
やり方:
1. 両手を頭の後ろで組む
2. 背中を丸めずに、ひじを後ろに開いていく
3. 10秒キープしてゆっくり戻す
4. これを5回繰り返す
肩甲骨の動きを促進し、胸の筋肉を伸ばす効果があります。
⸻
② タオルを使った肩甲骨エクササイズ
やり方:
1. タオルを肩幅程度に持つ
2. 両手を頭の上に伸ばし、タオルをピンと張る
3. そのままゆっくり頭の後ろまで下ろす
4. 10回繰り返す
広背筋や僧帽筋がストレッチされ、肩甲骨の可動域が広がります。
⸻
③ 壁を使った肩甲骨リリース
やり方:
1. 壁に背中を向けて立ち、テニスボールを肩甲骨の内側にあてる
2. 体を上下左右に動かして、コリを感じるポイントをマッサージ
3. 1か所につき30秒~1分程度行う
筋膜リリースにより、硬くなった筋肉をゆるめて動きをスムーズにします。
⸻
肩のケアを継続することが最大の予防策
インピンジメント症候群は、放置しておくと腱板断裂などの重症化につながる恐れがあります。しかし、早期に適切なケアを行うことで回復しやすい疾患でもあります。
特に、肩甲骨まわりの動きを意識したエクササイズやストレッチは、肩への負担を減らし、自然な動作を取り戻す鍵になります。
⸻
まとめ:今日からできるインピンジメント症候群ケア
肩の痛みを感じたら、まずは体を労わることが大切です。
そして、肩甲骨はがしをはじめとするセルフケアを日常に取り入れることで、予防と改善が可能です。
もう一度ポイントをまとめましょう:
• インピンジメント症候群は肩の組織が衝突して起こる痛み
• 姿勢改善や筋肉のバランスが重要
• 肩甲骨の柔軟性が鍵
• 無理せず継続的なケアが回復のカギ
肩の不調を感じたら、無理に我慢せず、早めのケアを心がけましょう。
ご予約はこちらから!