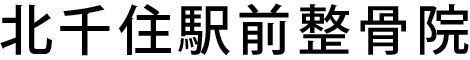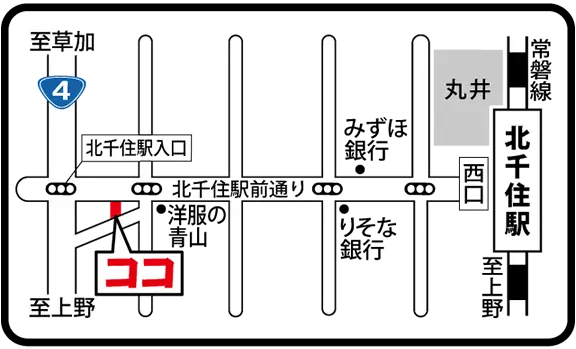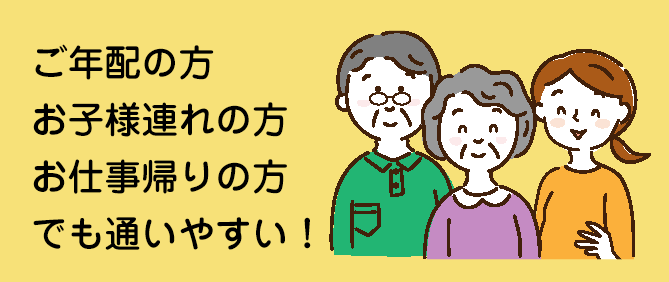「最近、肩が上がらなくなってきた…」「夜になると肩がズキズキ痛む…」そんな症状、ありませんか?
もしかするとそれ、五十肩かもしれません。
でも実は、五十肩には正式名称があるのをご存知ですか?
それが 「肩関節周囲炎(けんかんせつしゅういえん)」 です。
今回は、肩関節周囲炎(=五十肩)の原因・症状・治療法・セルフケア・予防法まで、わかりやすくまとめて解説します。
⸻
五十肩の正体「肩関節周囲炎」とは?
肩関節周囲炎は、肩関節の周囲にある筋肉・腱・靭帯・関節包などの組織に炎症が起こることで、**痛みや可動域制限(動かしにくさ)**が生じる疾患です。
中高年(40〜60代)に多く見られ、特に50歳前後に発症しやすいため、昔から「五十肩」と呼ばれるようになりました。
ただし、40代でもなる人は多く、「四十肩」とも呼ばれることもあります。
⸻
肩関節周囲炎の主な症状
肩関節周囲炎の症状は、大きく分けて3つの段階に分かれます。
① 炎症期(急性期)
• 肩の強い痛み
• 夜間痛(夜中にズキズキ痛む)
• 動かさなくても痛いことがある
② 拘縮期(こうしゅくき)
• 炎症は治まるが、肩が固まって動かしにくくなる
• 「腕が後ろに回らない」「上に挙がらない」
• 痛みはあるが、炎症期よりは軽い
③ 回復期
• 徐々に痛みが引いてくる
• 動かせる範囲が広がる
• しかし、放置すると完全に回復しないことも
⸻
なぜ肩関節周囲炎になるの?
原因ははっきりと解明されていない部分もありますが、主に以下のような要因が考えられています:
• 加齢による関節や腱の変性(劣化)
• 姿勢不良(猫背や巻き肩)
• デスクワークなどでの肩の使いすぎ・動かさなさすぎ
• 血行不良
• 糖尿病との関連(五十肩を併発しやすい)
⸻
放っておくとどうなる?
「そのうち治るだろう」と放置してしまう人も多い五十肩。
確かに自然に治るケースもありますが、半年〜2年ほどかかることもあります。
その間に肩の可動域がさらに狭くなり、関節が固まったまま元に戻らなくなるリスクも。
早期に適切な対処をすることが、回復を早めるカギとなります。
⸻
肩関節周囲炎の治療法
症状の段階によって治療方法が異なります。
以下のような対処法が一般的です。
🔹 急性期(炎症が強いとき)
• 安静(無理に動かさない)
• アイシング(冷却)
• 痛み止め(内服薬・湿布)
• 医療機関での注射や理学療法
🔹 拘縮期・回復期
• 温熱療法(温めて血行促進)
• 軽いストレッチ
• 可動域訓練
• 接骨院・整骨院での施術(手技療法・運動療法など)
※急性期に無理な運動を行うと、かえって悪化することもあるので注意!
⸻
接骨院・整骨院でできる五十肩ケア
五十肩は整骨院でも対応可能です。
以下のような施術を行います:
• 筋肉や関節周囲の緊張をゆるめる手技療法
• 肩の可動域を少しずつ広げる運動療法・リハビリ
• ハイボルト療法や超音波などの物理療法
• 自宅でできるストレッチや生活指導
柔道整復師が症状に応じた施術を行うので、医療機関との併用も可能です。
⸻
自宅でできるセルフケア・ストレッチ
回復期に入ったら、無理のない範囲で肩を動かすことが大切です。
簡単なストレッチ例(1日1〜2回)
• 壁伝いに手を登らせる運動(壁登り運動)
• お風呂上がりに腕を前後に軽く振るスイング運動
• タオル体操(背中で上下からタオルを持つ)
※痛みが強い場合は中止し、専門家に相談してください。
⸻
五十肩を予防するには?
予防には、日頃からの肩のケアが重要です。
• 同じ姿勢を長時間続けない
• 適度に肩を動かす(肩回し・ストレッチなど)
• 正しい姿勢を意識する
• 肩・背中・胸周りの筋力を維持する
• 冷え対策(クーラーの当たりすぎに注意)
⸻
まとめ:五十肩=肩関節周囲炎、放置せず早めの対処を!
「五十肩」は年齢のせいだけではありません。
姿勢や生活習慣が大きく関係しています。
もし、肩に違和感や痛みを感じたら、「そのうち治る」と軽視せず、早めに医療機関や接骨院に相談することが大切です。
当院でも、肩関節周囲炎に対する施術やリハビリを行っています。
「これって五十肩かも?」と気になった方は、ぜひ一度ご相談ください。